11.05
「善玉菌・悪玉菌・日和見菌」という概念は古い、「デブ菌」は悪玉ではなく日本人が強く生きてきたあかし 最新の研究で分かった「腸内細菌」の新常識(1/4) | JBpress (ジェイビープレス)
腸内細菌というのは非常に多様で、ビフィズス菌、乳酸菌、大腸菌などをはじめ、現在1000を超える種類が確認されています。 その中で、理想としては100種、少なくとも80種くらいは腸内(1/4)
情報源: 「善玉菌・悪玉菌・日和見菌」という概念は古い、「デブ菌」は悪玉ではなく日本人が強く生きてきたあかし 最新の研究で分かった「腸内細菌」の新常識(1/4) | JBpress (ジェイビープレス)
コロナ禍の衛生意識の向上や、偏った食生活により、現代人の腸内細菌の種類が減ってきているという研究結果がある。また、腸では幸せホルモンである「セロトニン」の9割が作られているため、腸内環境を整えることは、精神的な安定にもつながっていくという。私たちの健康の鍵を握る「腸内細菌」について、最新の研究結果から、令和の新常識を紹介する。(JBpress編集部)
(太田華代、腸活コンサルタント)
※本稿は『やってはいけない腸活』(太田華代著・手島麻登里監修、三笠書房)より一部抜粋・再編集したものです。
現代人の「腸内細菌の種類」が減ってきている
腸内細菌というのは非常に多様で、ビフィズス菌、乳酸菌、大腸菌などをはじめ、現在1000を超える種類が確認されています。
その中で、理想としては100種、少なくとも80種くらいは腸内に定着していてほしいところです。
しかし、実際にはこの腸内細菌が50種類を切っているケースも多く、なかには30種類くらいしか見えない人もいます。
コロナ禍の除菌ブームや衛生意識の向上などの影響によって、「現代人は腸内細菌の種類が少なくなっている」のです。
こういう状態にあって、前述したような「健康に良い○○は絶対に欠かさない」とか、「無農薬の野菜しか食べたくない」といった理由で偏った食事をしているとしたら、それは非常にマズいこと。
とにかく意識的にいろいろなものを食べて、そこに付いている多様な菌を取り込むことが、今後ますます大事になると言えます。
「善玉菌2割、悪玉菌1割、日和見菌7割」という説は間違っていた!
では具体的に、どんな菌が、どのくらいの割合で存在するのでしょうか。
良い菌としては、酪酸菌が20%、ビフィズス菌が10%、乳酸菌(虫歯などの口腔内細菌を除く)が5%はいてほしいところです。ほかにもさまざまな種類の「腸に良い菌」が存在しているのですが、それらすべての合計が40%くらいで推移するのが理想です。
また、悪い菌に関しては2%前後いる程度が理想で、残りは「よくわかっていない菌」になります。
実は、世間で頻繁に用いられている「善玉菌・悪玉菌・日和見菌」という概念は、最前線の研究者からするとあまりに古いものとなっています。
これまで腸に関する書籍やテレビの情報番組などでは、日和見菌について「善玉菌が多ければ善玉菌の味方をし、悪玉菌が多ければ悪玉菌の味方をする」と紹介されてきました。
この考えでは、「とにかく善玉菌を増やして悪玉菌を減らせば、日和見菌もそれに従う」ということになってしまいますが、そんなに単純なものではありません。
実際には、「善玉とも悪玉とも言いがたい菌がたくさんいて、その中には良い働きをする菌もいる」と言ったほうが正しいのです。
ましてや、「善玉菌2割、悪玉菌1割、日和見菌7割」という説は、現在ではすっかり否定されています。
 かつて良いバランスだとされていた腸内環境は、現在は否定されている。(提供:Kei/イメージマート)
かつて良いバランスだとされていた腸内環境は、現在は否定されている。(提供:Kei/イメージマート)
ある研究者によれば、「1割も悪玉菌がいたら、人はとっくに死んでいるよ」ということでした。
たしかに、悪玉菌にはO157やサルモネラ菌などの食中毒を引き起こす菌や、がんの発症に関わる菌もあり、普通なら1割もいるはずがないのです。
悪い菌」が少なすぎると風邪をひきやすい?
悪い菌の割合は2%前後だと説明されると、「そんなに少ないのなら、ゼロでも同じでは?」と感じる方もいるかもしれませんね。
ただ、「悪い菌がまったくいない」というのも、マズいのです。
前述したように、腸の中が乳酸菌やビフィズス菌のような「良い子」ばかりだったら、悪い菌が入ってきたときの抵抗力が弱すぎて、人は簡単に体調を崩してしまいます。そうした菌がわずかでもいることで、“用心棒”の役割を果たしてくれているのです。
実際に、最初の腸内解析で悪玉菌(と一般的にいわれる菌)の割合が0.5%と著しく低かった女性は、風邪を引きやすいことに悩んでいました。
詳しく話を聞くと、彼女は普段から手洗い・マスクを徹底し、除菌シートを持ち歩いているとのことでした。
もしかすると、それによって悪い菌が少なくなりすぎたことが、マイナスに働いていたのかもしれません。
ですから、悪い菌を必要以上に恐れないほうがいいのです。
悪さをしない大腸菌、腸の中にいてはいけない乳酸菌
お腹の中にいる悪い菌と言えば、多くの人が「大腸菌」を思い浮かべるのではないでしょうか。
しかし、大腸菌にも種類があり、食中毒を起こすような「病原性大腸菌」は1〜2割程度。残りの8~9割は、悪さをしない「非病原性大腸菌」と呼ばれるものです。
非病原性大腸菌の中には、私たちの腸内でビフィズス菌がビタミンを作り出す後押しをするなど、むしろ歓迎すべき働きをする菌さえいます。
一方で、良い菌もいろいろな顔を持っています。
たとえば、良い菌の代表格の一つといわれる乳酸菌は、現在見つかっているものが400〜500種類程度ありますが、日本人の腸内に見えているのは、そのうち30~40種類ほどにすぎません。
しかも、そこには口腔内細菌も含まれます。腸の中に口腔内細菌が見つかるのは、決して良いことではありません。しかし、大雑把な検査では、それも単純に乳酸菌としてカウントされます。
とある会社が消費者へのサービスの一環で行なっている検査では、乳酸菌が多ければポジティブなマークが付いた「良い結果」が返ってきます。しかし、そこに口腔内細菌が含まれているならば、喜んではいられません。
要するに、大事なのは表面的な「良い菌・悪い菌」という振り分けではなく、その内容だということです。
「デブ菌」は日本人が強く生きてきた証
「善玉菌・悪玉菌・日和見菌」以外にも、世間一般的にまだ知識がアップデートされていなかったり、誤ったイメージを持たれていたりする菌があります。その最たる例が、「デブ菌」と「ヤセ菌」です。
その名の通り、さまざまな腸内細菌の中でも、人を太らせる方向に働くグループをデブ菌、痩せさせる方向に働くグループをヤセ菌と、一般的に呼んでいます。
これ自体は間違いではないのですが、私としてはどうしても、「ちょっと乱暴な表現なのでは?」と思っています。
というのも、その呼び名から「デブ菌=人間を太らせる悪い菌」という印象が、世間一般に浸透してしまっているからです。
実際のところデブ菌は、エネルギーを効率的に吸収する「フィルミクテス門」というグループの菌で、決して悪い存在ではありません。むしろ「栄養をしっかり吸収するのに必要な菌」とも言えます。
日本人は、世界的に見てもデブ菌の保有量が多い傾向にあるのですが、これはかつて飢餓に苦しんだ経験から、「生き抜くため」に発達したものと考えられています。
デブ菌なくして、現代の私たちはいないということです。
実際、このグループの菌が見えることを指摘するとショックを受ける人が多い一方で、そうした人ほどしっかりとした食事ができていて、実は健康的であるというケースも珍しくありません。
繰り返しになりますが、デブ菌は悪い菌ではありませんし、少ないほどいいというわけでもないのです。
幸せホルモン「セロトニン」の9割は腸で作られる
最後に、意外と知られていない「腸」と「メンタル」の関連性についてお話しさせてください。
腸活にとってメンタルは、実はとても大事です。「腸脳相関」という言葉があるくらい、腸と脳はお互いに強く関与し合っていることが知られています。
腸は自律神経と深く関わっている臓器であり、腸が緊張状態にあれば交感神経が優位になりすぎてイライラしたり、睡眠の質が悪くなったり、血圧や血糖値が高くなったりします。
そういうときは、まず腸内環境を整え、緊張を緩めてあげれば、副交感神経が働いて落ち着いていきます。
腸内環境が乱れている人について、私が詳しく調査を進めたところ、「セロトニン」というホルモンの分泌が悪いことがわかりました。
セロトニンは、別名「幸せホルモン」とも呼ばれ、ストレスを緩和する方向に働きます。このホルモンの分泌が悪いということは、その人がストレスまみれであることを示しています。
実は、セロトニンの9割は腸で作られています。
また、やる気を出すホルモンである「ドーパミン」についても、その材料となる物質の多くが腸で作られます。
だから、腸内環境が悪ければ、そうした前向きなホルモンも十分に分泌されず、ストレス耐性も低くなってしまうのです。
私が見てきた限りで言えば、真面目な勉強家ほどセロトニンの分泌が少ない傾向があります。
それは、頑張りすぎてストレスが溜まりやすいという理由だけでなく、「やりすぎ」で腸内環境を乱してしまっていることにも原因があるのだと思います。
だからこそ、これから腸内環境を整えていこうと考えているあなたに心がけてほしいのが、「完璧を目指さない」ということです。
たとえば、「腸にとって、唐揚げなどの揚げ物を毎日食べるのは良くない」というのは事実で、それを守ってくれるのは大歓迎です。だからといって、「絶対に食べない」と決める必要はまったくありません。
毎日食べていた人なら、まずは週5回にして、あとの2回は魚を食べてくれれば、それだけでも腸内環境は良い方向に行きます。
このときも、魚の調理が苦手なら無理をせず、惣菜店で刺身や出来合いの焼き魚を購入して食べればOK。
あなたの腸は、こうした「いい加減な態度」も好きなのです。
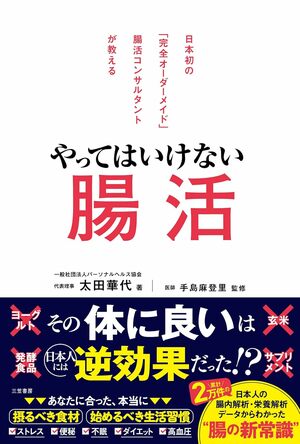
コメント
この記事へのトラックバックはありません。










この記事へのコメントはありません。